すごーく個人的な話になるのだった(しみじみ)
完結篇小説は、フツーの小説ではない。
そのことについてはまた考えて整理したいなーと思っているのだけど、とにかく、結論としては宿命的に賛否両論が渦巻く作品だと思うのだった。
賛否両論といっても、通販のレビューなどを除けば、個人サイトなどで散見する意見としては「否」が多い……ように見える。
もちろん、ネットで何か意見を言うと、どうしても否定的なアプローチが多くなりがち、ということもあるのだけど、たぶんそれだけではない。
インターネットを通じて発言するような習慣を持たない人でも、この作品を読んでスッキリ気持ちよくなる人はあまりいないだろうなーと思う。
じゃ、実際のトコロ、お前はどうなんだ、と問われたら。
もちろん、痛快で気持ち良い作品ではない、と断言できる。
ただ、私の場合、気持ち良いことと面白いこととは全く別の話なので、個人的には問題ない、というだけで。
特に、009のコアなファンは、辛かろうなと思う。
他人事のように言っているが、私も辛くないのかと問われれば、辛いなーと思っている。
ただ、私の場合、辛いことと面白いこととは(以下略)
……なのだった。
さかのぼって平ゼロの時にも思ったことだったが、私自身がそうであるように、009の場合は特に自分の中で勝手に作品のイメージが育ってしまった古い読者が結構多いので、こうしてメディアに乗る新作が出ると、実際に観たり読んだりする前からこれは違う、というトコロができてしまったりする。
それと作品そのものとは実は何の関係もないはずなのだけれど、作品を受け止める主体としては看過できない話なので、なかなか難しい。
完結篇については特に、003と009にそれぞれ恋人がいたりする……のが大問題になるようなのだった。もうその設定だけでダメ、という発言もよく見た。
が、今完結篇を読んで辛い、と感じる読者の多くは、もうそこを気にしていないように思える。
もちろん、私の辛いポイントも、始めからそこではない。
完結篇Ⅲで、サイボーグたちがどんどん斃れていったり、その過程で彼らが過酷な目にあったり、というところは、たしかにファンにとって厳しい描写だと思う。その象徴が、これまで禁じ手というか、むしろ聖域(笑)だった、003の負傷とそれにともなう非情な改造とで。
が、これもそんなに辛いのかというと、少なくとも私の場合は、そうでもない。
そして、作品の終わり方も、続編を絶対に許さない(笑)という点での寂しさはあるけれど、辛いというものではないのだった。
そう考えてみると、何がどうして辛いんだ、私(悩)と思ってしまうわけで。
ちなみに、「辛い」理由として、よく目にするのが、この小説が、構想ノートと異なっているからだ……という指摘だったりする。
つまり、ニセモノを見せられている・騙されているから苦痛なのだ、という理屈だろうと思う。
ただ、それを言っても実はあまり意味がない。
石ノ森さんは「作品」としては結局何も残していないからだ。石ノ森章太郎による「完結篇」はこの世に存在しないし、これからも存在しない。
要するに、彼自身がそのノートと同じ展開で作った完結篇など、どこにも「ない」モノなのだ。
そうしてほしかったと願うことはできるけれど。
「ニセモノ」と言うためには「ホンモノ」がなければならない。
その「ホンモノ」が存在しない以上、「ニセモノ」も存在しない。
何が言いたいのかというと。
つまり、「構想ノート」と違うというのは、この小説を読んだときの辛さを説明する根拠にならない、ということなのだった。そもそも、石ノ森章太郎が書いたとしても、そのノートと全く同じ展開になるとは限らないわけで。
ついでに言うと、もし石ノ森章太郎がこの完結篇と同じ展開の小説を書いたとしたら、それはホンモノだから辛くない……なんてこともあるはずがない。
もちろん、ノートを引き合いに出す場合、「石ノ森さんなら絶対こう書かない」という大前提があるので、論点がずれてしまうことになる。が、言うまでもないがその前提は、ただの希望であって、現実ではない。
実際に存在するモノが私に及ぼす作用について考えようというときに、この世に存在しないモノを自分の願望で勝手に想定し、それを根拠にすることはできない、ということなのだった。
構想ノート云々を抜きにして考えると、やはりこの小説の内容そのものと自分とを見つめるしかない。
私はどうして気持ち良くなかったり、辛かったりするのか。
この作品と、これまでの「009」とは何が違うのか。
その異なる本質は何か。
ついでに言うと、私はしまむら映画については別に辛さを感じていない。
では、映画と完結篇は何が違うのか。
そんなわけで。
どうして気持ち良くなかったり辛かったりするのか……と一生懸命考えたとき。
私が思い出すのは、ものすごく個人的、なおかつかなり素っ頓狂な話に飛んでしまうのだが、特攻隊員として21才で亡くなった母方の伯父のことなのだった。
母の実家の仏壇のある部屋には、ずらりと並んだ曾祖父母や祖父母などの遺影とともに、航空兵姿の伯父の肖像が掲げられている。
祖母は生前、伯父の死についてほとんど何も語らなかった。
が、祖母が亡くなったあと見つかった遺品の中に日記のような断片的なメモがあって、伯父についても「こどもに先立たれるのはなによりもつらいことです」という言葉があったのだという。
尋常小学校にしか通ったことのない祖母は、選挙で投票するために、大人になってから字の練習をしたのだという。新聞を読むことも欠かさなかった……というのだから、読み書きは好きだったのだと思う。
それにしても、作文、のようなことをするのは難しかったはずだし、祖母がそうした文章を書いているということは誰も知らなかったのだ。
そんな祖母が一生かけて書き残したわずかな文章の中に、やはり伯父のことは書かれていたわけで。
書かずにはいられなかったんだろう、と、母や伯母たちは言うのだった。
よく言われるように、伯父もまた、どこでどのように亡くなったのか、というような国からの知らせは一切なかったし、もちろん遺骨もありはしない。
そんな中で、遺族としてどのように手がかりを追ったのかはわからないが、これまでにこんなことがわかっている。
伯父は鹿児島から飛び立ったらしい。
特攻機には一人で乗り込むのが通例だが、後ろの席に通信員が乗ることもあった。伯父はその役目にあたったのだ。
その話を聞いたのは、もう私が30代になり、伯父が亡くなった年齢をとうに過ぎた頃だった。
今でも、そのことをふと夜に思い出したりすると、眠れなくなる。
夢であればいいのに、他の人のことであればいいのに、と繰り返し思う。
ただ、つらいと思う。
祖母は生前、何度もうちに泊まりにきた。
子どもだった私は、自分が夏休みに祖母の家へ行くのと同じことだとしか思っていなかったが、子どもたちの中でも一番郷里から遠い土地で、狭くて粗末なアパート暮らしをしている末娘のところにわざわざ来るというのにはそれなりに色々な事情があったのだ。
そのひとつが靖国神社への参拝だった。
祖母は、上京したときには靖国参拝を欠かさなかった。
が、いつも一人で行き、母たちが同行を申し出ると、きまってこう断ったのだという。
「行かなくていい。あそこにはなんもない。おらだけでいいんだ。」
祖母の死後、母と一緒に靖国神社を訪れたことがある。
伯父の慰霊のためというより、その頃東京の大学に通い始めた私が「おのぼりさん」をやっていたのを、母がおもしろがり「そういえば行ったことがないから。兄さんに会いに行こうかな。連れて行って」と言い出したからだ。
母は伯父と直接会ったことがない。伯父が家を離れた後で生まれたのだった。
そういう意味では、きょうだいといっても実感はないのだと、母は言う。
母と並んで手を合わせ、祈った。
大学での専攻の関係で、靖国神社については様々なことをかなり多方面から学んでいたし、その功罪についてもよくわかっているつもりでいた。
が、伯父がここにいるのだと思うと、そうした知識や思考を超えた不思議な高揚感があった。偉大な人と自分がつながっているのだ、というような気持ちに近かった。
母もしみじみと、本当に大した立派なトコロねえ、と嘆息し、でも、と付け加えた。
「ばあちゃんは、ここに○○(伯父の名)はいないんだって、よく言ってたけどね」
……で、だから何なのかというと(悩)
完結篇について考えているとき、このことを思い出したのは、もちろん完結篇に「特攻」という言葉が繰り返し出てくるからだと思う。
それは、自己犠牲による攻撃を指している。
考えてみると、009たちの決め技は昔から特攻のみといっても過言ではない(倒)
というといい加減な感じがするが、彼らのやり方で闘い抜けば、最後にはそうなってしまうというか(遠い目)
特攻は美しい。それは間違いない。
が、同時に醜悪でもある。
どうにも受け入れがたい現実なのだ。
伯父の死を思い、どうにもやりきれない気持ちになるとき。
私はいつも、どうにかしてこう思おうとする。
伯父は、故郷や家族を守るために……自分にできる全てがそれであると信じ、自らの意志で闘うために飛行機に乗ったのだ。
無理矢理引きずられ、乗せられたのではない。
……と。
でも、無理なのだった。
だって、20代になったばかりの、善良で健康な青年だった伯父が、死にたかったはずがない。生きたかったに違いないのだ。
明日も、明後日も、その次も。
私がそうであるように。
生きたいと願いつつ死に自ら赴く。
だから自己犠牲であり、美しい。
それは人間にしかできない、自由の本質を具体化する行為でもある。
その意志を崇高だと私たちは感じる。
他人のことなら、そう感じることは容易だ。
でも、それが家族……個としての自分にとって、特別な個である人の上に起きたことであるならば、簡単なことではない、というより無理じゃないか、と思う。
でも、それが特攻だ。
だからこそ、特攻なのだった。
完結篇を読むのが辛いのは、おそらく、009たちが本当の自己犠牲を……特攻を行っていて、そして、それを私が、ただの物語ではなく、私にとってかけがえのない個の上に起きた現実……肉親の上に起きた現実のように感じるからなのではないか。
そういうことではないのかな、と思うのだった。
一方で、私は、特攻隊を題材にした演劇を見て、感動したりしたこともある。
この感動と、伯父を思うときの苦しさは背反しつつ両立する。
おそらく、祖母も、だから靖国神社に参拝した。
かけがえのない息子の受け入れがたい死を、遠い崇高なモノと感じさせてくれるに違いないその場所に。
が、そこには「何もない」ことをも、祖母は知っていた。
息子の死は理不尽で受け入れがたい事実なのだ。そこになんら変わりはない。
ありふれた話といえば、そうだ。
現実そのものは、いつもむごたらしい。
その現実の中から、観念的に取り出したモノを用いて構築したフィクションは、空しいが限りなく美しい。
それだけのことなのだけど。
完結篇の場合、そうした現実とフィクション、そして私たちとの関係がねじれている。
まず現実があり、その中で生きる人間がフィクションを生み出す、というのがフツウの順序だ。
完結篇では、それが逆になった。
私は「009」がフィクションであることを前提として長年読んでいたわけだが、石ノ森章太郎はそのフィクションは実は現実なのだと突然宣言し、ただ宣言しただけではなく、そういうフィクションとして、「009」を再構築してしまった。それが、完結篇だ。
小説を書き上げたのは息子の小野寺さんだったが、再構築の仕組み……構図は変わっていない。
そして、完結篇の作品としての特殊性はその構図そのものにある、と私は思う。
その構図の中で、私の現実は、否応なしに作品の中に引き摺り込まれていく。
それは具体的に言うと、邪鬼が私の生きるこの現実世界に現れているような実感があるとか、そういうことではない。
作品を読みながら、私が、フィクション上で009たちに起きたことを現実を感じるのと同じ感じ方で受け止めてしまう、ということなのだと思う。
だから辛い。
009たちはこれまでにも過酷な闘いを生きてきた。
しかし、それはヒーローとして、フィクションとしての闘いだ。
009と002が生きながら燃え尽きる現実としての熱も痛みも、流れ星に涙する私には決して届かない。
だから感動できた。
完結篇は、Ⅰが出たときにはその設定が一見素っ頓狂に見えることに疑問の声が上がった。
Ⅱでは、特に009の章において、それまでの彼のイメージと違うじゃないか、という感想が目立った。
ここまでは、何というかごくフツウのフィクション作品に対する反応・批判であって、条件が揃えば他の作品でも起こりうることだと思うのだった。
が、Ⅲの辛さはそれらとは全く異質である、と私は思う。
辛いのだけど、こんな辛さがあるのか……!という興味の方が勝っている、というのが今の私の状態なのだった。
当然だが、フィクションに現実の辛さが混入してしまうのは「失敗」だと言える。
身も蓋もないが、失敗した作品なら、市場に出回るはずがない。
しかし、「009」だからそれができた。
もちろん、そもそも「009」だから、小野寺さんは失敗だろうがなんであろうが、書かなければならなかったのだし、石ノ森さんも「息子」にそれを託さなければならなかったのだ。
石ノ森さんが「息子」にそれを託したのは、たぶん「誰にも書けない」小説だったからだ。
が、誰かが書かなければならない。それは本当は自分だった。
だから、自分に一番近いモノにそれを託したのだ。
小野寺さんは、誰にも書けない小説をとにかく書いた。
石ノ森章太郎の息子であるということから逃れられないように、それが逃れられない宿命だったから。
誰にも書けない小説なのだから、できあがったモノは当然フツウの小説ではない。
でも、出版された。
それが、「009」だからだ。
こんなことが可能である、ということ自体が、「009」という作品がバケモノである証拠だと思う。
もちろん、石ノ森章太郎はバケモノだ。
が、「009」はそれをものみこむバケモノだったのだ。
これまた非常に個人的な感想なのだけど、私は思春期の頃に「009」に出会い、それから、なぜかこの作品から離れられずにここまで来てしまった。
それはたぶん、アタマのおかしい思春期に嵌まったせいで、変なスイッチが入ったからだ……と、自分に原因があるとしか思っていなかったのだけれど。
もしかしたら、原因は「009」の方にあるのかもしれないのだった。
|
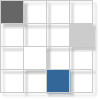
![]()